夜中に突然泣き出したり、寝かしつけてもなかなか眠らなかったり──。多くのママ・パパが一度は悩む「寝ぐずり」。
生後数か月から始まり、幼児期まで続くこともあるこの現象には、実は赤ちゃん特有の発達や環境が深く関係しています。
本記事では、寝ぐずりの基本知識から原因、効果的な対策、そして実際に悩みを乗り越えたママたちの体験談までを幅広く紹介。
「なぜ寝ないの?」「どうすれば泣き止むの?」と不安を抱えるママ・パパに寄り添いながら、今日からできる改善のヒントをお届けします。
寝ぐずりとは?基本知識

寝ぐずりの定義と特徴
「寝ぐずり」とは、眠いはずなのに赤ちゃんが泣いたり不機嫌になったりして、なかなか寝付けない状態のことを指します。
一見“わがまま”のようにも見えますが、赤ちゃんにとっては眠りに入る準備が整っていないサインでもあります。
主な特徴は以下の通りです:
- 目をこすったり、耳を触ったりする
- 抱っこしても泣き止まない
- 眠そうなのに遊びたがる
- 寝付いてもすぐに起きる
これは大人でいえば「寝たいのに頭が冴えて眠れない」状態に近いもの。赤ちゃんの脳が発達する過程で、眠り方を学んでいる途中に起こる自然な現象なのです。
赤ちゃんの寝ぐずりはいつまで続く?
寝ぐずりのピークは生後6〜8か月頃。この時期は「人見知り」や「分離不安」が始まるため、ママの姿が見えないだけで泣いてしまうこともあります。
その後も、
- 1歳前後:歩き始めの興奮期
- 2歳頃:イヤイヤ期の自己主張
- 3歳頃:昼寝卒業の過渡期
と、発達段階ごとに形を変えながら寝ぐずりは続きます。ただし、個人差が非常に大きいのが特徴。早い子では1歳半で落ち着く一方、3歳を過ぎても寝かしつけに時間がかかる子もいます。
ひどい寝ぐずりの原因とは?
寝ぐずりの背景には、以下のような要因が複雑に絡んでいます。
- 過剰な刺激:日中に新しい体験をしすぎて興奮状態に。
- 睡眠不足:眠りのリズムが崩れるとさらに寝つきが悪くなる。
- 環境の変化:引っ越し、保育園デビュー、家族構成の変化など。
- 体調不良:鼻づまりや便秘、発熱などの不快感。
- 甘え・安心の欲求:ママやパパのぬくもりを求めて泣く。
「どうして寝ないの?」と悩む前に、その日の赤ちゃんの一日を振り返ることが解決の糸口になります。
寝ぐずりの背後にある要因

睡眠環境とその影響
寝室の温度や照明、音は赤ちゃんの睡眠に大きな影響を与えます。理想的なのは、室温20〜24℃・湿度50〜60%。明るすぎる照明やテレビの音は刺激となり、眠りを妨げます。
また、寝る直前のスマートフォンの使用も要注意。親の画面の光が赤ちゃんの体内時計を狂わせることがあるため、就寝1時間前は「光と音を控える」のがベストです。
生活リズムの重要性
赤ちゃんの体内時計は、まだ未発達。毎日同じ時間に起き、食べ、遊び、寝る――という一定のリズムが整うことでようやく「眠る準備」がスムーズになります。
特に朝日を浴びることは重要。朝日を浴びてから約14〜15時間後に眠気を誘うホルモン「メラトニン」が分泌されるため、朝の光を習慣づけることが寝ぐずりの改善につながります。
昼寝との関係性
昼寝の取り方も寝ぐずりに直結します。
- 昼寝が長すぎる → 夜の寝付きが悪くなる
- 昼寝が短すぎる → 過疲労で眠れなくなる
月齢に応じた昼寝時間の目安は次の通り:
| 月齢 | 回数 | 1回の目安 |
|---|---|---|
| 0〜3か月 | 3〜4回 | 1時間前後 |
| 4〜6か月 | 2〜3回 | 1〜2時間 |
| 7〜12か月 | 2回 | 1〜1.5時間 |
| 1〜2歳 | 1回 | 1〜2時間 |
「昼寝を削れば夜寝る」は誤解で、昼寝も夜の睡眠の一部と考えることが大切です。
効果的な対策方法

抱っこや授乳のタイミング
眠いサイン(あくび・目をこする・ぼーっとする)が出たら、早めに寝かしつけを。タイミングを逃すと興奮して眠れなくなります。
抱っこや授乳は「寝かせるため」ではなく、安心させるための時間と考えるのがポイント。
「添い寝しながらトントン」「抱っこで背中を優しくさする」など、スキンシップを通じた安心感が眠りのスイッチになります。
安眠を得るための環境作り
安眠には「五感を落ち着かせる」工夫が効果的。
- 視覚:照明は間接光で柔らかく
- 聴覚:ホワイトノイズやオルゴールを活用
- 嗅覚:洗いたての寝具の香りで安心感を
- 触覚:ガーゼ素材や綿素材で肌触りを整える
さらに、「おやすみルーティン」を作るのもおすすめ。「絵本を読む→電気を消す→トントン」のように、毎晩同じ流れを繰り返すことで赤ちゃんは“もう寝る時間”と学習します。
無料の育児講座やコンサルタントの活用法
最近では、自治体や助産師による無料の睡眠相談・オンライン講座も充実しています。プロのアドバイスを受けることで、客観的に生活リズムを見直すきっかけになります。
また、民間の「ベビースリープコンサルタント」も人気。生活環境・月齢・家族構成に合わせてカスタマイズされたアドバイスをもらえるため、寝ぐずりの長期的な改善が期待できます。
夜泣きと寝ぐずりの違い
「夜泣き」は、眠っている最中に突然泣き出す現象。「寝ぐずり」は、眠る前に泣くという点で異なります。
夜泣きは睡眠サイクルの切り替えがうまくいかないことが原因。一方の寝ぐずりは「眠りに入る準備が整っていない状態」。つまり、寝ぐずりを減らすことは夜泣き予防にもつながるのです。
寝ぐずり対策の具体例
おすすめの寝かしつけ方法
- 背中トントン法:一定のリズムで軽く叩く
- 添い寝しながら呼吸を合わせる:親の呼吸音で安心感を与える
- スリーピングソング:毎回同じ歌で眠りの合図に
- おくるみ:新生児期は体を包むことで安心感アップ
「うちの子に合う方法」を見つけるまで時間はかかりますが、“儀式”として定着させることが成功のカギです。
我が家はこの中のまさに「スリーピングソング」を取り入れて、一番の効果を感じました。
赤ちゃんの頃から「きらきら星」の歌で寝かしつけていた末っ子は、もうすぐ4歳になる今、眠くなると「お母さん、きら星歌って」とお願いをしに来たり、おもむろにyoutube musicで「きらきら星」の曲を選んでかけたりするので、「眠いサイン」が分かりやすくなっています。
寝ぐずりに有効なツール
ホワイトノイズマシン
赤ちゃんが落ち着くとされているホワイトノイズ。お腹の中から聞こえていた音に似ているそうです。
このホワイトノイズマシンはナイトランプにもなりますしホワイトノイズも3パターンあるだけでなく、体内音や雨音、川のせせらぎ音などもあり赤ちゃんだけでなく大人にとってもリラックスできる音が多数収録されています。
また嬉しいのがメモリー機能。前回流したお気に入りの音をすぐに再生してくれます。
タイマー機能もあるので一緒に寝てしまって夜通し流れていた!なんてことも避けられます。
寝かしつけぬいぐるみ
寝るルーティーンのおともになってくれるぬいぐるみです。
こちらも赤ちゃんがリラックスできる音楽が多数収録されています。
寝るときはこのぬいぐるみと一緒、という習慣作りをすることができます。
リラックスできる音、プラネタリウム、そして寝るときのおともという3つの役割をこなしてくれるこんなアイテムもあります!
機械部分は取り外しが可能なのでぬいぐるみだけ洗えるというのもうれしいポイントです。
これらのツールは「赤ちゃんが自分で眠りに入る練習」をサポートしてくれます。
ママとパパの役割の違い
寝かしつけはママだけの仕事ではありません。パパの抱っこだと泣き止む子も多く、“いつもと違う刺激”がリセット効果をもたらすことも。
また、パパが夜の一部を担当するだけで、ママのメンタル負担が大きく軽減します。「交代制」ではなく、「チーム制」で乗り越えることが大切です。
寝ぐずりに悩むママたちの体験談

ギャン泣きのときどうする?
「もう何をしても泣き止まない!」そんな夜は誰にでもあります。あるママは「いったん部屋を暗くして、深呼吸してから抱き上げる」ことで落ち着いたそうです。
赤ちゃんが泣き続けているときは、ママの焦りが伝わってさらに泣くこともあります。まずはママ自身の心を落ち着かせることから始めましょう。
成功体験とそのコツ
多くのママが共通して語るのは、「毎日同じルーティンを崩さない」こと。寝る前の行動を固定化することで、赤ちゃんが“安心して眠れるパターン”を学習していきます。
育児の悩みを共有する場所
SNSやオンラインコミュニティで、同じ悩みを持つママたちとつながるのも心の支えになります。「寝ぐずりがひどいのはうちだけじゃない」と知るだけで、心が軽くなることもあります。
まとめと今後の展望

安眠を取り戻すためにできること
寝ぐずりは成長の一部。焦らず、生活リズムと安心できる環境を整えながら、「眠る力」を育てる時間と考えましょう。
子育てを楽しむためのヒント
泣き声の多い夜も、数年後には「そんな時期もあったね」と懐かしく思える日が来ます。「今日もよく頑張った」と自分を労いながら、少しずつ改善を重ねていきましょう。
📘この記事のまとめ
- 寝ぐずりは赤ちゃんの発達サイン
- 原因は生活リズム・環境・安心感の不足
- 改善には一貫したルーティンが効果的
- ママ一人で抱え込まず、チームで乗り越えることが大切
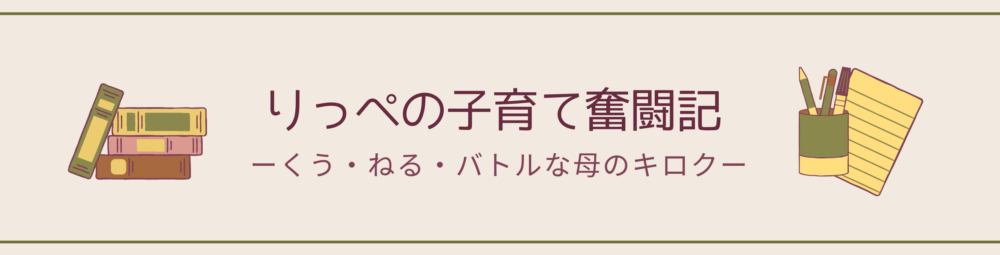
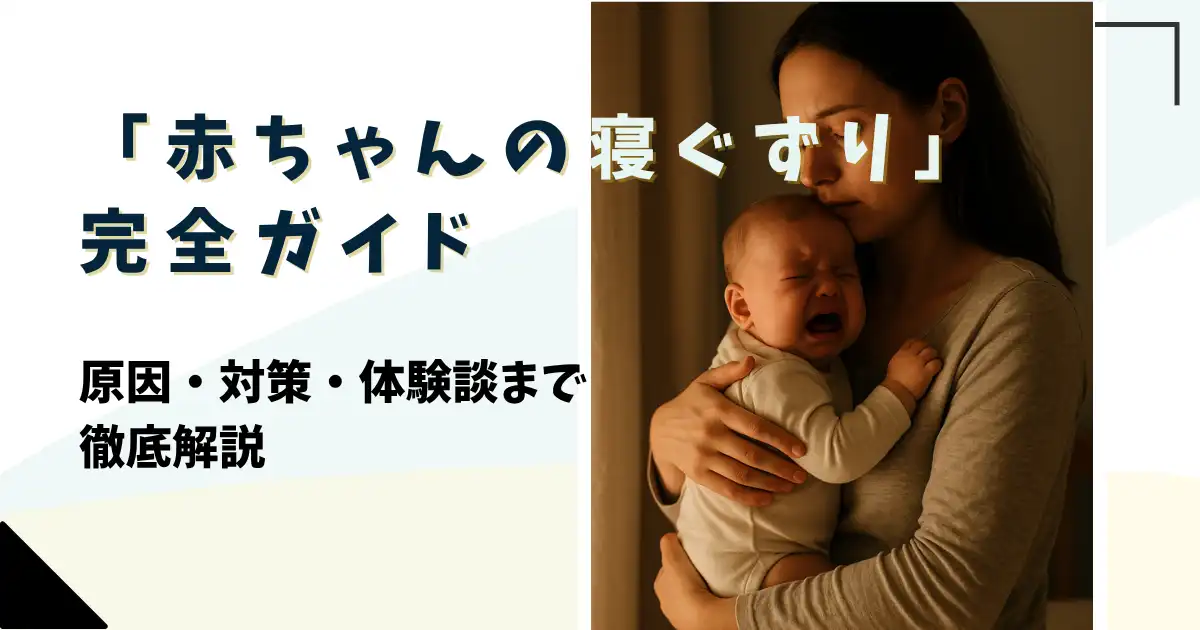
コメント