3歳児健診で「お母さん、上手にやってるから大丈夫よ」と言われた。
けれど私は、心のどこかで「本当に大丈夫なのかな」と感じていました。
2歳のころから癇癪が多く、感情の切り替えが苦手な息子。違和感を抱えながらも、誰にも相談できずにいた私に、年長の春、担任の先生がかけた言葉は「一度プロに相談してみてください」でした。
ショックと同時に「やっぱり」とも思ったあの日から、私と息子の発達支援が始まりました。
この記事では、発達グレーゾーンの子を育てる母としての戸惑いと気づき、そして支援につながるまでのリアルな体験をお話しします。
年長の春、「一度プロに相談してみてください」と言われた日

長男が年長に上がる直前の個人面談で、担任の先生からこう言われました。
「一度、プロに相談してみてください」。
理由は「感情のコントロールが苦手だから」ということでした。
その言葉を聞いた瞬間、頭が真っ白になりました。
“プロに相談”という響きが、まるで我が子に「何か問題がある」と突きつけられたようで、胸の奥がぎゅっと締めつけられたのを覚えています。
けれど、同時に「まさか」ではなく「やっぱり」という感情もありました。
というのも、長男は2歳のころから癇癪がひどく、感情の切り替えも上手ではなく、ずっと“何か生きづらさ”のようなものを感じていたからです。
3歳児健診で伝えた“違和感”──それでも流されたあの日

思い返せば、3歳児健診のときも、私はその違和感を伝えようとしました。
保健師さんに「そのほかに気になることなどありますか?」と聞かれたとき、私は勇気を出して話したのです。
「癇癪が多く、感情の切り替えが難しいこと」「叱っても泣くだけで話が届かないこと」。
でも今思えば、私は“人に頼るのが苦手”な性格で、どこか強がってしまっていたのかもしれません。
きっと、深刻に見えなかったのでしょう。
保健師さんは優しく笑って「お母さん、上手にやってるから大丈夫よ」と言いました。
その言葉は一見励ましのようで、当時の私には“流された”ように感じました。
その瞬間、「あぁ、この違和感は誰にも伝わらないのかもしれない」と心の中に小さな孤独が残ったのです。
「ほら、言ったじゃん」と思った担任の言葉
だから、年長の春に担任の先生から「プロに相談を」と言われたとき、私はショックでありながらもどこかで「やっぱり」と思いました。
“あのときの違和感は間違っていなかったんだ”と。
療育センターが人気でなかなか予約が取れないことは知っていました。
それでも私は、帰り道を歩きながらスマホを握りしめ、すぐに電話をかけました。
結果、3週間後に予約が取れたときは、ホッとしたような、でも怖いような、複雑な気持ちでした。
初めての発達検査とカウンセリング
発達検査と行動観察の結果、息子は「自閉スペクトラム症かもしれない」と言われました。
感情のコントロールの未熟さなどの幼さがある一方で、足し算・掛け算ができるなどの“能力の凸凹”が見られる──それが理由の一つでした。
でも当時の私は、「計算ができるのは公〇式に通っていたから。それで“凸凹”と言われても…」と、素直には受け入れられませんでした。
それでも、“この子が少しでも生きやすくなるなら”と気持ちを切り替え、定期的なカウンセリングを受けることにしました。
臨床心理士さんとの出会い

カウンセリングでは、臨床心理士さんと息子が一緒に遊びやタスクをこなし、息子の様子を観察しながら、親の私にも関わり方のアドバイスをしてくれました。
毎回1時間ほどのセッションの中で、私は「子どもとどう向き合えばいいのか」という長年の悩みを少しずつ話していきました。
そんなある日、先生が言ってくださった言葉を今でも忘れられません。
「とてもよく、まっすぐに向き合っていらっしゃいますね」「お母さんのやり方、とてもいいと思います」。
私はそう言われたとき涙があふれそうになりました。誰かに「あなたは間違っていない」と言ってもらえたことで、張りつめていた心が一気にほぐれたのです。
トラブルを抱えたときの“宿題”ルール
息子は、自分が正しいと思ったときに引かない性格で、友達と(時に先生とも)トラブルになることもありました。
その相談をしたとき、先生が教えてくれた方法はとてもシンプルでした。
- その場で解決しようとせず、「宿題」として持ち帰り、家で親に話すこと。
- 親は「いつでも話していい」という環境を保つこと。
この二つを意識するようになってから、私の中の“焦り”が少しずつ消えていきました。
息子が落ち着いて話せるようになると、トラブルの裏にある気持ちを理解できるようになり、親子の距離が縮まっていくのを感じました。
半年のカウンセリングを経て見えてきたもの
約半年にわたるカウンセリングを終えて、息子が劇的に変わったかと聞かれれば、正直わかりません。
癇癪を起こさなくなったのは、成長の一部かもしれません。
でも確実に変わったのは、私の心です。
「私はこの子とちゃんと向き合えている」という肯定感。
「焦らず、見守ることも支援のひとつなんだ」という気づき。
その二つを手に入れたことで、私は“孤独な子育て”から少しずつ抜け出せたのです。
息子が自分のペースで前に進めるようになったのは、私が“信じる力”を取り戻したからかもしれません。
同じように悩むママへ伝えたいこと

発達グレーゾーンの子育ては、正解がない世界です。
「うちの子は他の子と違う」と感じても、誰かに相談したり、支援につながるのは勇気がいることだと思います。
でも、その一歩を踏み出すだけで、見える景色が変わります。
私も最初は「相談=問題」と思っていましたが、今は「相談=味方が増えること」だと感じています。
もし今、あなたが3歳児健診や園での指摘に戸惑っているなら、どうか自分を責めないでください。
あなたが不安を感じたその感覚こそ、子どもを理解する第一歩です。
発達支援センターや療育は“特別な場所”ではなく、子どもが自分らしく生きるための小さな助けをくれる場所です。
そこにたどり着くまでのすべての出来事──あのショックも、焦りも、涙も──今ではすべて、私と息子にとって大切な「きっかけ」だったと胸を張って言えます。
あなたとお子さんにも、きっと同じようにやさしい光が差す日が来ます。
どうか、焦らずに。大丈夫です。あなたの歩みが、もうすでに子どもにとっての“支援”です。
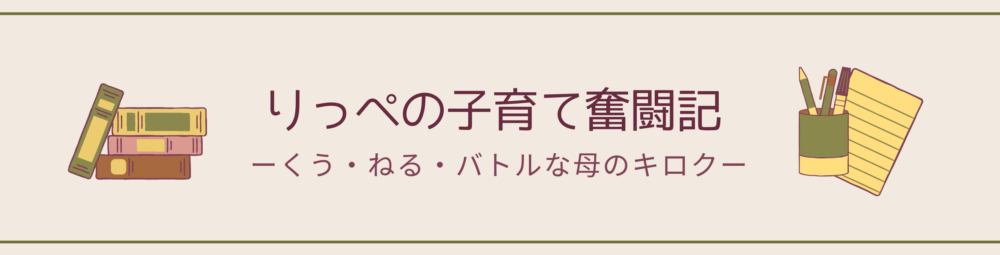
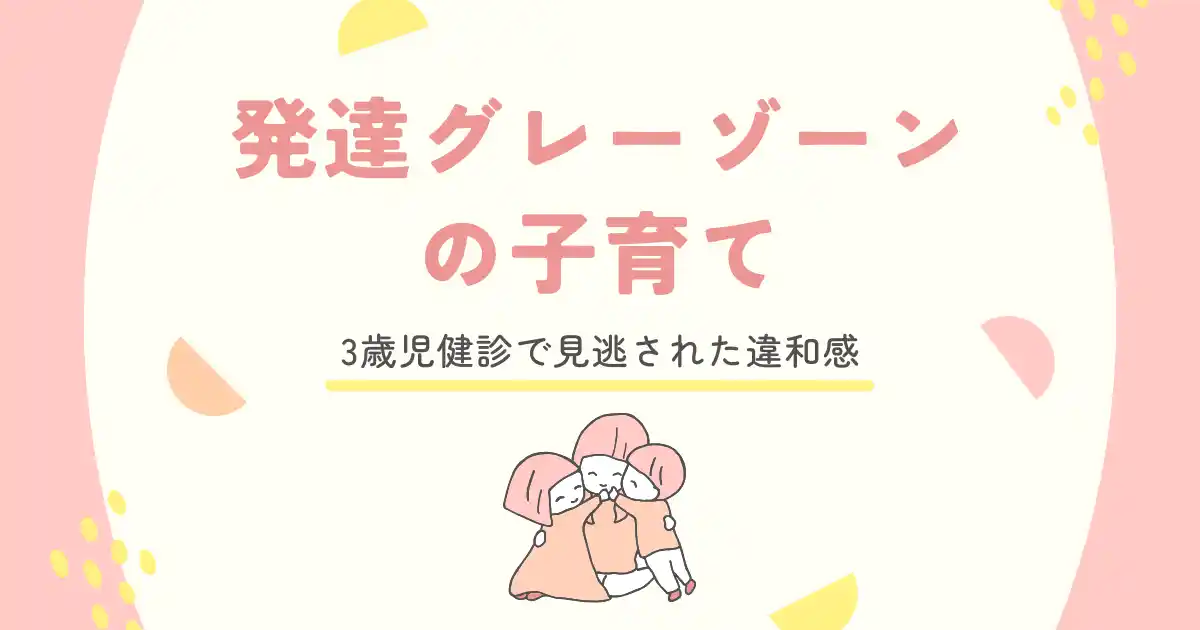
コメント